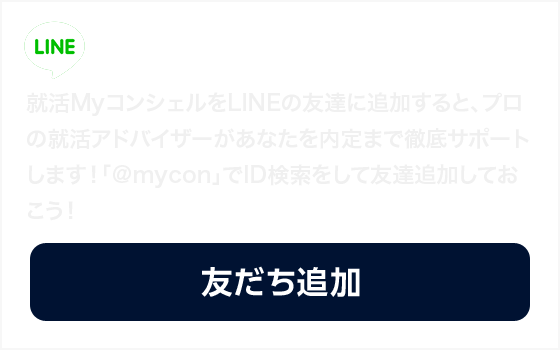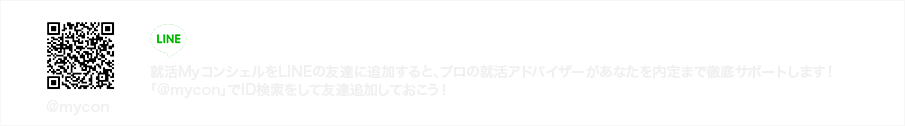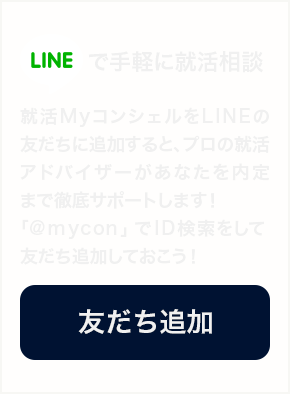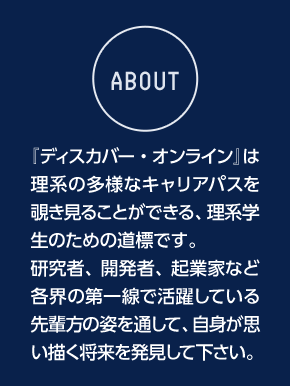2015/12/28 UPDATE
- Interview
- 女性
- 文系就職
タブーに切り込むメディア・アーティストに聞いた、「一緒に仕事をしたい」と思われる“理系”の人材像

大根を触ると喘(あえ)ぎだす装置「セクハラインターフェース」や、ヒト型ロボットPepperの胸部を女性の乳房にアレンジした「ペッパイちゃん」の生みの親である、メディア・アーティストの市原えつこ氏。彼女が手がける作品はセンセーショナルなものが多く、しばしばネット上を賑わせている。
数人でチームを組んでプロダクトを作り出している市原さんだが、自身はアートディレクション……すなわち作品コンセプトを生み出す立場であり、複雑なコードも書けなければ回路を設計することもできない。しかも、平日はIT企業でウェブデザインを生業とする、ごく普通の会社員でもある。そんな奇想天外なキャリアを歩む市原さんに、自身のこれまでの半生と今後の展望、彼女の目線から見た“理系のリアル”について語ってもらった。
[ PROFILE ]
市原えつこ(いちはら・えつこ)
1988年、愛知県生まれ。早稲田大学文化構想学部表象メディア論系卒業。学生時代より、日本特有のカルチャーとテクノロジーを掛け合わせたデバイス、インスタレーション、パフォーマンス作品の制作を行う。主な作品に、大根が艶かしく喘ぐデバイス「セクハラインターフェース」、虚構の美女と触れ合える装置「妄想と現実を代替するシステムSRxSI」、脳波で祈祷できる神社「@micoWall」などがある。2014年には「妄想と現実を代替するシステムSRxSI」が、文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門審査委員会推薦作品に選出された。
市原えつこHP:http://etsukoichihara.tumblr.com/
デジタル・ネイティブはぬり絵がお嫌い?
大学では文系色の強い環境に身を置いていたにもかかわらず、在学中からテクノロジーを積極的に活用したプロダクトを作ってきた市原さん。一体いつから理系的な技術に興味を持ち始めたのだろうか。
「父親が国立大学の理工学部卒業で、電子機器などを扱う商社の営業職でした。なので、昔から家には設計図や回路図、電子製品のパーツが散らばっていたんです。そんな父の影響からか、私も小さい頃からデジタルデバイスによく触れていて。とくに、パソコンで絵を描くことは好きでしたね」
最初は父の手ほどきがあったものの、すぐに自学自習でパソコンを使いこなすようになった市原さん。そこから彼女の興味は、技術ではなく美術分野へと向いていく。
「絵を描くことを通して美術やアートの世界に強くひかれるようになり、高校生の頃から美大の予備校に通い始めました。けれども、そこではっきりと気づいてしまったんですが……私、アクリル絵の具ではみ出ないように塗るような、細かいことをするのが本当に苦手で。『こんなのパソコンで一発じゃん!』って叫びたくなってしまうんです(笑)」
“絵を書くのが好き”というシンプルな入り口から美術の世界に足を踏み入れた市原さんだったが、知れば知るほどに“得体の知れない怖い存在”になっていったと言う。
「現代美術の作品は時代の欲望などが生々しく反映されていたりして、ものによっては負のオーラを感じることがあって……。それと、高校3年の時に村上隆さんの芸術評論を読んで、画壇と呼ばれる業界内の癒着体質や学閥(がくばつ)・学歴主義などを強く感じ、『美術業界、なんかうさん臭い!』と思ったんですね。そうした違和感が積もっていった結果、美大に行くことは断念して、メディアについて幅広く学べそうな早大の文化構想学部を進学先に選びました」
社会とオープンにつながれる“メディア・アート”の魅力
あまり細やかな職人的作業は好きではなく、コンセプトを考えてさくさくとスピード感を持ってものを作るのが好きだったと話す市原さん。そんな彼女の関心がアートに回帰したのは、大学2年生の時だった。当時慕っていた先生の授業の一貫で、“科学技術と芸術文化の対話の促進”をテーマに設立された「NTTインターコミュニケーションセンター(ICC)」足を運ぶ機会を得た。そこで初めて“メディア・アート”というジャンルに出合い、強くひかれることとなる。
「メディア・アートは最先端の産業や研究など、芸術外の技術的分野とアートを接続させることの多い表現方法なので、一般的な美術業界に感じていたような閉塞感がなかったんです。そこに一種の爽やかさや風通しのよさを感じとれたから、肌に合ったのかなと」

皆さんは美術館に漂う荘厳な空気に、訪れた自分が作品に試されているような感覚を抱いたことはないだろうか。歴史的な背景や作者の経歴など、正しい知識を持っていないと作品を理解できないのでは……このような考えから「美術はなかなか踏み込みにくい領域だ」と考えている人は多いだろう。市原さんもかねてから美術分野の排他的な風潮に抵抗感を覚えていたそうだが、メディア・アートにはそれも感じなかったと話す。
「美術の世界には、美術を唯一の生業としている人や業界に精通している人のみを受け入れ、他を寄せつけない雰囲気って少なからずあると思います。一方でメディア・アート界には、自分で会社を持っていたり、大学で研究をしていたり、それぞれ社会でまったく別の役割を果たしながら作品づくりをしている人も多いんですよ。だからこそ排他的な空気が生まれないし、作られる作品も現実社会と繋がっているものが多い印象があります。私も昔から“社会にちゃんとコミットしたい”という欲求は強く、そこにも親和性を感じたことから、メディア・アートにハマったんだと思います」
“豊穣なアダルトカルチャー”を再発見するための、“触ると喘ぐ大根”
学生時代にメディア・アートの面白さに気づいた市原さんは、在学中に『セクハラインターフェース(以下、SI)』という“触れた大根が喘ぎだす装置”を発表。機能の説明だけ聞くとまるで意味の分からない装置の開発に着手した経緯を、市原さんは次のように語ってくれた。
「ICCでの出合い後、私はメディア・アート研究者である草原真知子先生のゼミで、メディア・アートについて真剣に研究するつもりでした。3年次にそのゼミに入れたところまではよかったのですが、肝心の草原先生が自身の研究のためにアメリカの大学へ行ってしまって(笑)。ただ、代わりにゼミを担当することになったのが、日本文化である連歌をビジュアルイメージで行うプラットフォーム『連画』などを手がけた“システム・アーティスト”の安斎利洋さんだったんですね。顔合わせの初日、安斎先生は私たちゼミ生に向かって突然『俺は君たちをアーティストにする!』と言い出して……(笑)」

(SI実演の準備をする市原さん)
想定外の流れではあったものの、自身がメディア・アートに携わる上で最適な環境を得た市原さん。先生の指導の下、どんなテーマで作品を作ろうかと模索した結果、たどり着いたのが“エロ≒性”だった。
「安斎先生はゼミでさまざまなワークショップをしてくれたのですが、その過程で私は『どうやら自分はエロに興味があるらしい』ということに気づいたんです。当時は広告やコピーライティングの勉強もしていたのですが、そこで人から褒められるのも不思議と“エロ”に関連するものばかりで。『興味もあるし向いているのならば、性文化について本腰を入れて研究しよう』と思い、ピンク映画を観にいったり、ストリップ劇場に行ったり、男根崇拝の神社に行ったりしました。そのリサーチの中で、日本には歴史的に“豊穣なアダルトカルチャー”が存在することに気づいたんです」

(取材時には大根がなかったので、代わりに白菜とにんじんを喘がせてくれた)
学究心の赴くままに、日本の性文化についてフィールドワークを続けた市原さん。最終的にたどり着いたのが、熱海にある『熱海秘宝館』だ。一般には日の目を浴びない秘密のもの(≒エロいもの)が多く展示されている、世にも珍しい施設である。彼女はここを訪れて「秘宝館は日本のメディア・アートの結晶だ!」とのインスピレーションを受け、“性”をテーマにしたアート作品を作ろうと思い立った。
「当時見ていたメディア・アートは無機質で洗練されたものが多かったのですが、今ひとつピンと来ていなくて。秘宝館で、ナンセンスで土着的な感覚が入り混じった展示物の数々を見て『これだ!』と思ったんですよ。本能的で土着感があり、どことなく日本の文化を匂わせるメディア・アートを、自分は求めていたんだと悟りました。性的なものって、現在の日本社会の中で抑圧、規制される対象になっていますよね。けれども、日本人ってエロに対してもともと“豊穣・健康・神聖さ”を見出していた民族なんですよ。これは男根崇拝の神社を訪問した際に、直感で得たイメージでもあって。こうして、自分たちのルーツになっている“性”のメンタリティに訴えかけるインタラクティブな……触って感じられるプロダクトを作ろうという考えに至り、SIの構想が生まれたんです」

(久しぶりの実演だったからか、取材陣をそっちのけで楽しみ始める市原さん)
その後大学のゼミで「SIを作りたい!」と言ったところ、ゼミのメンバーにはドン引きされたのだとか。しかし、そこで唯一賛同してくれた1人の先輩(現在テクニカル・ディレクターとして活躍している渡井大己氏)との出会いに恵まれて、SIの開発がスタート。その先輩も文系で回路設計の経験など一切ないが、自身に眠る創造の衝動に駆られたのか、いつの間にか独学で電子工作を会得し、瞬く間にSIのプロトタイプを作ってくれたそうだ。
(SIの公式プロモーション動画)
SIは後に機能を拡張し、代替現実システム(Substitutional Reality System)を組み合わせた『妄想と現実を代替するシステム SR×SI』に進化を遂げる。これは「SR laboratory」の技術提供のもと開発したプロダクトだ。被験者はモニター内蔵のヘッドギアを装着してSI……もとい、大根に触れる。モニターには艶めかしい女性が映し出されており、SIの反応によって映像が変化する。つまり、被験者はこの装置によって「美人の足を触って相手が喘いでいる状況」を疑似体験することができるのだ。これを外から見ると、被験者は「変なヘルメットを被って大根を触りながらニヤニヤしている人」にしか見えないので、非常にシュールな絵面になる。
「SR×SIの制作では、コンセプトメイキングからコンテンツまで、チーム全員で考えながら進めていきました。SRの概念や本質を勉強することと現実と虚構のシーケンスを行き来するための空間演出、あとは女の子のキャスティングが特に大変でしたね」
“性”から“死”へ、現代のタブーの扉をノックし続ける
今後エロネタで何か企んでいることはあるのか聞いたところ、「エロはやりきった感があるのでもういい」と言う市原さん。現在は、今年8月に文化庁の「メディア芸術クリエイター育成支援事業」に採択された『デジタルシャーマンプロジェクト』 に着手中だ。
「ここで主に扱いたいテーマは“死”や“弔い”です。これらは昔から絶えず人類が続けている営みですが、現代においては必要以上に隠蔽されているような気がしていて。今では科学技術も発達しているので、もっと現代向けに“死”や“弔い”の形もデザインされるべきだろうという思考から、『デジタルシャーマンプロジェクト』を発足させました。具体的な内容は未定なのですが、新しいテクノロジーを活用して“弔い”を取り巻く人の感情を新しくデザインし直す試みができたらいいな……と考えています」

『デジタルシャーマンプロジェクト』の具体案としては、Pepperのイタコ化……つまり、“ロボットに死者の痕跡を疑似的に宿らせる仕組み”を考えているとのこと。市原さんは「思想などといった肉体以外の“個人情報”を残すための装置は、これからどんどん増えていくのでは」と予測している。彼女はこのプロジェクトを研究するにあたって、参考として多くのSF映画を鑑賞し、その中で“人工知能で死者を蘇らせる”という表現が何度も取り上げられていることに気づいたのだとか。最近の映画で言えば『her』や『トランセンデンス』なども、この類に当てはまるだろう。「死んだ人をもう一度蘇らせる」という行為は、人間が長年抱いてきた潜在的な望みなのかもしれない。
市原さんは『デジタルシャーマンプロジェクト』が、多くの人の“死”について考えるきっかけになってくれたら……と願いを込めている。彼女の表現の根底にあるのは、“エロ”や“死”など人々が公にしたがらないもの、けれども生命の営みの中に当たり前に存在するものに対する“偏見の払拭”なのだ。
昨今の日本では“死を考えること=ネガティブなこと”と捉えている人が多いと思います。けれども、私は『自分はこういう風に死にたい!』と、もっと楽しく考えてもいいんじゃないかなって感じるんです。生物に平等に訪れるものが、そんなに酷く、誰しもにとって悲しいものだとは思えないから。自分がこのような表現を続けることによって“死について考えること=ポジティブでもいいこと”に変えていきたいです」
一緒に仕事をしやすい理系、しにくい理系の差とは?
精力的にアーティスト活動を展開する市原さんだが、普段はIT企業で働くデザイナーでもある。通常の業務もなかなか忙しいと苦笑いする彼女は、いつ創作活動をしているのだろうか。
「平日は毎日出勤して会社員をしていますが、昼休みなどには個人活動に関するメールのやり取りをしたり、企画書を作ったりしています。会社ではあまり残業はしないようにしているので、夜はガッツリ自分の創作に充てていますね。週末はストレスが貯まっていると外で思いっきり遊ぶんですけど(笑)、普段はシェアオフィスにこもって作業しています」
市原さんが勤める企業は規模が大きく、職場で最新のテクノロジーに触れる機会も多い。周りには優秀な技術者もそろっていて、個人の活動で困ったときには相談に乗ってくれることもあるそうだ。「会社での業務や人とのつながりが創作の肥やしになることは“会社員アーティスト”の大きなメリットだ」と、彼女は語る。

会社や個人で活動している中で、技術者など理系の人たちと仕事をする機会も多い市原さん。ものづくりのディレクションを執る立場からすれば、自分の構想を元にプロダクトを作ってくれる“技術者との相性”は重要なポイントだろう。彼女は「理系の人でも、話しやすい人、話しにくい人がいる」と言い、その違いについて説明してくれた。
「理系の人のとっつきやすさは“技術をわかりやすく翻訳して、詳しくない人に説明する意識”の差かな、と感じています。難しいことを簡単に説明するのって、根本から理解しているからこそ可能なんですよね。まれにですが……難しい言葉を多用することが格好いいと思っているような人がいて(笑)。そういう方とは話がかみ合わなくて、だんだん話すモチベーションが下がってしまいます。コミュニケーションが取りやすく、ゴールに向かってお互い寄り添えっていけるような技術者の方だと、一緒に仕事がしやすいです」
理系の皆さん、自分のスキル、楽しそうに自慢してください。
一言で“理系”と言っても、社会に出ればその働き方は実に多種多様だ。IT分野に限って見ても、フロントエンジニアとバックエンドエンジニアでは業務内容は大きく異なる。最近ではUI・UXデザイナーなど新しい業種も出てきており、今後も世の中の変化に合わせて、さまざまな働き方が生まれてくるだろう。これからの時代、どんな“理系人材”が必要とされるのだろうか。これまで多くの技術者と関わってきた市原さんに、意見を伺った。
「IT分野で言えば、技術力に加えて経営能力もある人が圧倒的に強いと思います。あと、これはちょっと感覚的な話なのですが……その業界の権威である人たちに怒られたり、嫌われたりするくらいの人の方が、これからの世の中を変えていく可能性とパワーがあるんじゃないかなって。大学でも、教授の言うことを素直に忠実にやるだけ人ではなくて、勝手にいろいろと作って外に出て発表しちゃうタイプの人ですね。自分の作品を自慢気にプレゼンする人って楽しそうで、そういう技術者の周りには自然と人が集まってきて、いきなり面白いプロジェクトが始まってたりするんですよ。ドヤりながらもわかりやすく、そして楽しそうに自分のことを話せる理系の人は、すごく魅力的だなって思います」

最後に、自身が理系ではないから答えにくいか……とは思いつつも、「理系学生に向けて何かアドバイスはあるか」と市原さんに聞いてみた。彼女は少し悩んでから「直感を大切にしてください」と言い、こう言葉を続けた。
「理系の皆さんは総じて、論理的な思考力には十分長けています。だからこそ、論理とは別次元にある“感覚”や“感情”の行く先に意識を向けるだけで、きっと面白い発見がたくさん見えてくるはずです。いま学生で『何か面白いことをしたい!』とくすぶっている人は、直感的に『面白そう』と感じた場所に積極的に行ってみてください。視野を広く持ち、理系以外の人たちと多くつながりを持つことで、自分自身のレベルアップやステージチェンジのきっかけになると思います」

(彼女の作品である“露出狂から仏へクラスチェンジした仏界のカリスマ”『HIROSHI♂』との貴重な2ショット)
市原さん自身も、自分の活動については本当に楽しそうに語ってくれた。ものづくりを愛し、つくったものを愛している人、その愛を周囲の人間に伝える努力をしている人は、文理にかかわらず強く人の心を惹きつけて離さない。理系の畑にいる人間にとって、彼女のようなユニークなコンセプトデザイナーやディレクターたちとの出会いは、将来の可能性を無限に広げる重要なターニングポイントになり得るだろう。
(取材・文/石原龍太郎、写真/石毛健太郎)
オススメ記事
-

2016/1/25 UPDATE
- Interview
研究って難しいけど、おもしろい。 ――東工大生に新しい視点を提供す…
-

2015/12/22 UPDATE
- Interview
ワクワクできる未来に向かって――4000年ぶりの革新を生んだスマート…
-

2015/12/28 UPDATE
- Interview
タブーに切り込むメディア・アーティストに聞いた、「一緒に仕事を…